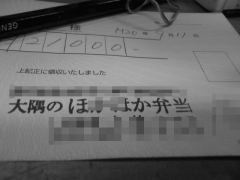学研・大人の科学付属のアナログシンセ、SX-150。
amazonに注文するもバックオーダーに入ってしまって、いつ届くのかと待っているうちに軽く忘れていたりしたのですが、
ようやく先日届きまして、早速組み立ててみました。
何故かモノクロで写っているパッケージ。この中に、アナログシンセの本と付録一式が入っています。
スチロールの箱にきれいに収まっています。もちろん箱には、
と、箱の側面という見えにくい場所に小さなシールで表記してあります。さすがは学研。
抜かりないようで抜かってるような・・・。
早速開封。
組立は、説明書通り順番にやっていけば、絶対に完成します。ハンダゴテが必要?と思われた方もご安心下さい。チップ部品はおろか、
大物部品も含めて全て基板に取り付けられております。リード線もコネクタを差し込むだけ。
電子機器の製作というよりは、組立(アッセンブリ)ですね。実際、家電製品の組立工場では、
この調子で同じ製品を毎日大量に作っていたりするわけですから、この程度のものでも、日本の製造現場を体験出来るというわけで、
有意義だと言えるでしょう。多分。
ネジが小さいので、老眼っぽい人には苦労があるかも知れませんが、15分もあれば完成します。
出来たら早速鳴らしてみます。
手前に見えている黒い帯状の部分に、手に持っている棒を当てると音が出る仕組みで、左右に振ると音程が変わります。
これで4オクターヴ程の音域があるということですが、楽器として演奏するにはかなりの困難が伴うかと思われます。
ということで音は適当に鳴らしつつ、ボリュームをいじって音の変化を楽しむことになるわけですが、これがことのほかおもしろい。
説明書には、こういうセッティングにすると、こういう音が出ますよという例が載っているのですが、こんなちっぽけな物で、
こんなにいろんな音が出るというのは、ちょっと感動モノです。
Matrix6と比べてみました。同じアナログシンセ同士です。というのは無理がありますが、基本的には同じモノなんですよね。
あとはこれで何か演奏でも出来ればいいんですが、正確な音程を取る練習をしないといけませんね。
鍵盤をつけることを考えた方が良さそうな・・・気もしますが、少しがんばってみましょう。笑
—–
台風やや接近で天気が悪い日は、こうやってインドア遊びするのも悪くないです。
昨日は朝っぱらから鶏飯食ってました。
—–
台風が来るのか来るのか・・・と予報図を見ていたのですが、やっぱり来るようですね。
迷走しつつも遠ざかって行く雰囲気だったので安心してたのですが、それが一転。直撃コース。
—–
そんな緊迫ムードのさなか、某所へイベント手伝いに行っていました。
前日入りと言うことで、
久々のリンガーハットで遅い夕食。どこでいつ食っても同じ味なのが頼もしい。
次の日の夕食は一転。豪華なすきやきです。何故か野外。
野外と言えばバーベキュー!という人がほとんど占めるキャンプ場での夕食。この固定概念がどこから来てるのかは知りませんが、
別に何でもいいじゃないかと私は思います。ただし美味しければ。バーベキューもたまにはいいですけどね。
翌日、発注するのを忘れていて、慌てて頼んだ弁当屋。
HKHK亭・HMに続く第3勢力・・・では無いようですが、実に微妙なネーミングしています。汗
—–
そんなこんなで帰って来たら、職場を流れる川に
こんな奴が繁殖してるようです。
遊びに来た子供がいとも簡単に捕まえて来たので、魚好きなSさん(鋭意募集中)
に聞いてみたらブルーギルだとのこと。
特定外来魚ということで捕るのもいけないそうなので、事情を説明してリリース。
その子供はすっかりテンションダウン(せっかく捕まえたのに・・・)していましたが、
そもそもこんな魚を放流した奴はどこのどいつだと。
こういうの、自然の生態系を乱すというのもありますがね。
せっかく捕まえた魚を家で飼ってみることも出来ないという現実を生みだしたことも罪だと思いますよ。
そもそも川に居た魚なんて、持って帰ったってすぐ死ぬんだからという意見もあるでしょうが、
それを知るためには捕ってきた魚を自分で死なせてみないとわからない。少なくとも自分はそうでしたが。
だから、命というものを身近に感じられる機会を奪ってしまうような、今回の出来事にはとても憤りを覚えます。
ちょっと大げさかも知れませんけど・・・。
—–
種子島土産の南泉15度を飲みつつ、そんなことを考えた夜でした。





 (コンビニ弁当ですが・・・。)
(コンビニ弁当ですが・・・。)